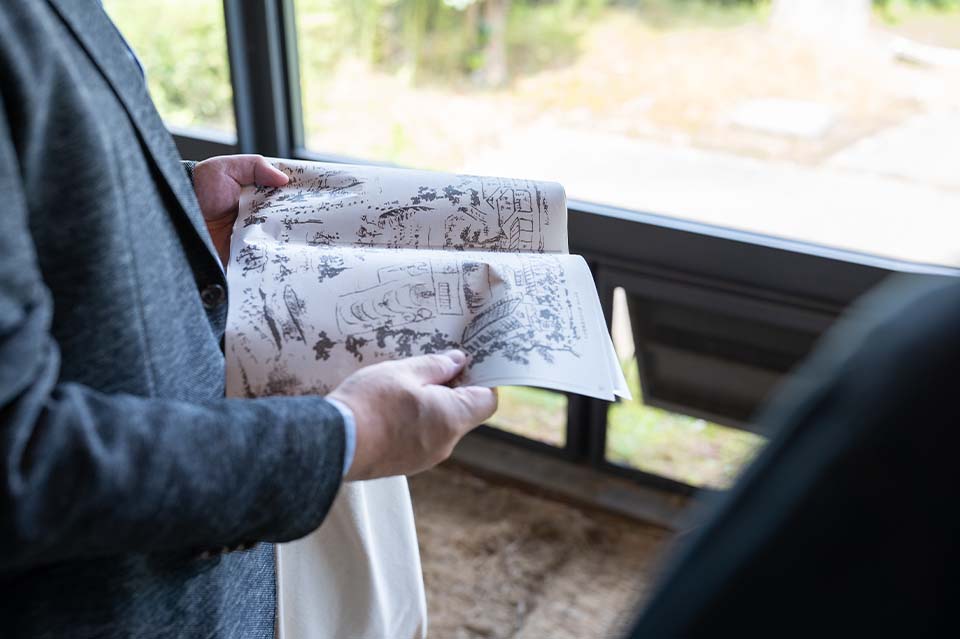#09
流通を担い作り手を支え、産地を守り続けてきた問屋
KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。ここまで作家や職人たちの技や技の受け継がれ方に注目してきましたが、第8話と9話では「産業と九谷」をテーマに、産業の面から九谷焼を支えている企業を訪れます。今回伺ったのは、大正時代に創業し長年九谷焼を支えてきた老舗問屋「伊野正峰」と、インターネットを駆使して現代の卸業を営む「北野陶寿堂」です。
時代の流れ共に変わる問屋のあり方や流通の仕組みについて、主に戦前から戦後を「伊野正峰」に、昭和後期から令和にかけてを「北野陶寿堂」にお聞きしました。産地を代表する問屋2社へのインタビューを通じて、九谷焼業界の変遷や流通の変化をたどります。

昭和、平成、そして令和へ、
インターネットを武器に時代の波を乗りこなす

-
案内してくれた人
北野広記さん
北野陶寿堂の三代目。東京の広告会社での勤務を経て、家業を継ぐため2009年にUターン。2019年より代表取締役。 2017年にオリジナル九谷焼ブランド「ハレクタニ」をスタート。また、2020年には九谷焼の情報発信サイト「九谷焼mag」を立ち上げた。目指すのは「世界中の家庭に九谷の和食器の彩りが広がること」。

- 北野:
- 創業者である祖父はもともと兄弟で商売をしていたのですが、1972年に独立して、新たに会社を設立しました。しかし昔は九谷焼を扱う大きい会社がたくさんあり、祖父は新規開拓に大変苦戦し先行きも見通せなくなって、当時、東京にいた父に「家に帰ってきて手伝ってほしい」と呼び寄せました。
- 秋元:
- その頃、お父さんは東京で何をしていたのでしょうか?
- 北野:
- 祖父の紹介で陶器業界に就職して、売り場で販売をしていたそうです。当時はどんどん独立して商売を始める会社が出現したような時代で、九谷焼の産地には既に大手の会社も多くありました。
- 秋元:
- 最盛期で、問屋は何軒くらいあったのですか?
- 北野:
- 大小含めて200軒ほどあったそうです。
- 秋元:
- すごい数だなあ。70年代は国内需要も相当あった時期ですよね。
- 北野:
- そうですね。バブル前からどんどん右肩上がりで、贈答用の需要もかなりあり、花瓶のような大きな商品が本当に売れる時期でした。ただ、弊社は美術品として九谷がたくさん売れているタイミングでスタートしたのですが、それでも業界内では後発の企業だったので、営業をしても門前払いされるなど顧客の獲得に苦労していました。

- 秋元:
- 当時、問屋とお客さんとの関係というのは相当固定していたのでしょうか?
- 北野:
- そうですね。あとは人情というか、そういう面も大きかったと思います。
- 秋元:
- 卸先はどのようなところが多かったのですか?
- 北野:
- デパートを中心に一般の陶器店などに卸していました。父は家業に戻ってから、お客さんが全くいない状況のなかで、「担ぎ売り」という営業スタイルで仕事をしていました。日本全国、北海道から九州、沖縄まで出張して、商品サンプルやカタログを入れたバッグを担いで、「九谷焼の業者ですが、いかがですか」って一軒一軒歩いて回るわけです。
- 秋元:
- 昔は対面が基本でしたもんね。
- 北野:
- そうですね笑。父が全国各地を歩き回って熱心に営業したことで、少しずつ取引先も増えていきました。大型百貨店に行ってもなかなか相手にしてもらえなかったので、今まで九谷焼の取引をしていなかったような量販店にもアプローチをして、徐々に九谷焼を扱ってもらえるようになったそうです。

- 秋元:
- 量販店で取り扱う九谷焼は、どういった商品が多かったのでしょうか?他のお店と比べて、取り扱う商品に特徴などはあったのですか?
- 北野:
- ほとんど花瓶でした。価格帯が安くて量産ができるという点で量販店に向いていたんですね。それから父はどんどん新規開拓をして、規模の大きい商社と取引をしたり、全国の小売店ともつながりを作ったりするなかで、少しずつではあるのですが、これまで取引がなかった百貨店などから「最近がんばってる会社だよね」と少しずつ目を向けていただけるようになりました。
- 秋元:
- 当時の一番のヒット商品は何ですか?
- 北野:
- ダントツ花瓶で、年間数万本を販売していました。花鳥柄の転写や吹き付けという技法(※)で連山を描いたものが多く、価格帯は5000円以下くらいでした。昔は結婚式の引き出物として九谷焼の花瓶が人気だった時期もあったそうですが、そこでもまとまった数の注文が入っていたんです。
(※)吹き付け/釉薬をコンプレッサーで吹き付けるように塗りつける方法。
- 秋元:
- 量販店以外には、どのような会社と取引があったのでしょうか。
- 北野:
- ギフト関係や通販会社などですね。いくら花瓶が売れていても、需要がいつまでも続くわけではないだろうということで、父は新規開拓に励みました。その結果、九谷では後発の会社だったにも関わらず、ほぼ一代でそれなりの規模の会社になります。

- 秋元:
- お父さんが帰ってきてから短期間で会社が大きくなったというのは、新規顧客を開拓する際の、目の付け所がユニークだったのでしょうね。加えて冠婚葬祭が華やかになった時代だったので、取り扱っていた商品がそんな時代ともマッチして贈答用としての需要を取り込むことに成功したと。
- 北野:
- 一昨年父は他界したんですけど、本当に人のつながりを大事にしていて。人情で商売するタイプだったので、九谷の他の業者さんが断るような仕事も、お客さんから依頼されたことであればまず応えられるように努力する。すぐ断るようなことはしないというポリシーを持っていたんです。象徴的なエピソードが、後々うちの主力になる骨壷です。
- 北野:
- 骨壷を作り始めて20年くらいになるでしょうか。はじめに東京の大手葬儀社の社長さんから「豪華絢爛な九谷焼の骨壷を作ってみたい」と相談をいただいたんです。都内ではお墓を建てる人がだんだん少なくなっていて、その代わりとして納骨堂の利用者が増えてきていたのですが、骨壷は真っ白なデザインのものが多くてちょっと寂しいと。骨壷はお墓の代わりになるのものなので良いものを作りたいということで、何軒も当たられたそうなんですね。しかし他社からは「うちでは難しい」と敬遠されてしまったらしく、そんななかで父は相談を受けてとにかく「サンプルを作ってみます」と対応をし、結果うちのヒット商品にまで育ちました。

葬儀社は骨壷のヒットを受けて骨壷専門店をオープン。関東圏に12店舗まで拡大した。
- 秋元:
- お参りに行ったときに、こちらの方が気持ちも明るくなりますね。
- 北野:
- そうですね。実際にご覧になられた方の多くがこの骨壷を選んでくださるそうです。それから今日に至るまで、骨壷は超安定商品と言いますか、景気にも左右されず毎月一定の売り上げを保っている商品になります。
- 秋元:
- 全体の売り上げのうち、骨壷はどれくらいの比率を占めているのでしょうか?
- 北野:
- 現在は数パーセントですが、私が12年前に帰ってきた当初は、全体の売り上げの2割を占めていました。景気が悪い時期に骨壷は売れ続けたので、これが下支えしてくれたからこそ従業員の雇用を守れました。コロナ禍を経験して改めて、事業を多角化したほうが全体への影響は少ないと身に染みて思いました。会社を支える柱となるような事業をたくさん持っておくことが大切ということです。
- 1
- 2
- 3
- 4