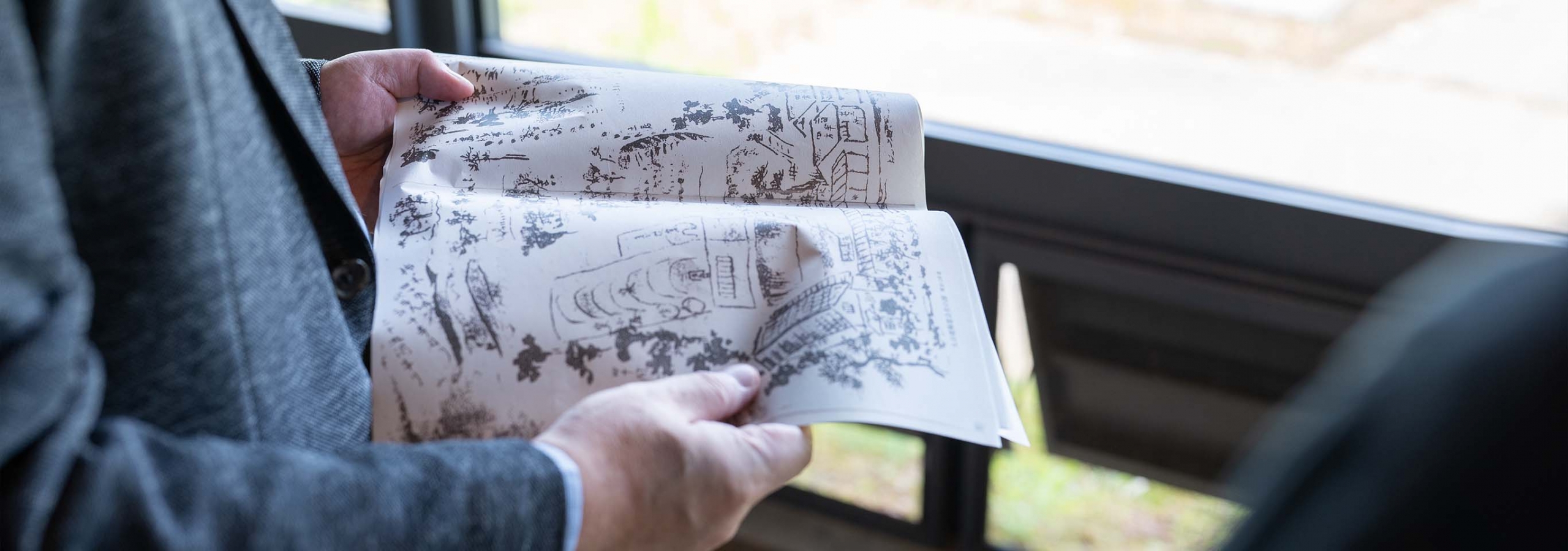

#02
九谷焼の系譜 吉田屋窯、そして古九谷へと遡る
KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで、九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。2021年度は “技法”と“伝承”をキーワードとして、九谷の魅力を、系譜を紐解きながら探っていきます。
第二話では、いよいよ九谷焼の流れを求めて、まずは文政9年(1826)に九谷村(現・加賀市山中温泉九谷町)から山代温泉越中谷に窯が移された吉田屋の窯跡がある「加賀市九谷磁器窯跡展示館」へ。大聖寺の豪商吉田屋伝右衛門が古九谷の美に憧れて開いた窯であり、吉田屋風と呼べる洗練された和絵具による色絵磁器を生産。国指定史跡として保存されています。
その後は場所を移し、更に山奥へ。古九谷の生産地だった加賀市山中温泉九谷町にある「九谷磁器窯跡」を訪れます。今からおよそ360年前、吉田屋窯から数えれば約170年前に作られた二つの登り窯と絵付窯の跡が残り、国指定の史跡となっています。
歴史の奥深さや当時の息遣いを感じる二つのスポットを通じて、古九谷から現代九谷の礎と発展の経緯を探ります。

古九谷、そして、初期の吉田屋窯跡まで
九谷焼のルーツが見つかった場所
- 中矢:
- あちらに九谷1号窯跡が見えますね。位置関係としては九谷古窯の1号窯のそばに吉田屋の窯が築かれたということになります。
- 秋元:
- 吉田屋は1号窯に敬意を表して、この場所で始めたのでしょうか?
- 中矢:
- 大いにありますね。あちらに門が見えますが、近辺に水車があって、スタンパー(※1)のようなことをしていたみたいです。それから杉の木が生えている辺りは後藤田(ごとうだ)と呼ばれていた田んぼになりますが、そこが恐らく後藤才次郎(※2)の屋敷跡じゃないかと言われています。ですので工房も、あの辺りにあったのではないかと。
(※1)粘土の製造方法の一つ。杵のような機械を使って陶石を粉砕し、それを「水ひ」という方法により、粘土質になる部分だけ取り出す。
(※2)加賀大聖寺藩士。藩の命令により肥前有田で製陶法を習い、帰藩後に古九谷窯を開いたと言われている。
- 中矢:
- 一方で吉田屋は古九谷の窯跡や工房跡に敬意を表して、あえて全く同じ場所には行かないんですね。少し離れたところで「ここでやらせていただきます」というような感じだったのではないでしょうか。
- 秋元:
- 相当リスペクトしていますね!
- 中矢:
- 後藤才次郎がどんな人物かというのも知っていたので、後藤の名前が付く場所に何かを建てるということはなかったんですね。古九谷の窯跡を色んな意味でリスペクトした上で、吉田屋伝右衛門はここに窯を築いたということです。

- 中矢:
- みんなここで「あれが古九谷を焼いた窯の跡地だ!」というのを意識しながら作陶していたんですよね。職人たちはすごく嬉しかったと思いますよ。ただ冬は雪がすごかったものですから、山代に移転する話になって。ここで使っていた窯道具も含め、全部持って山代に下りたんです。ここで九谷が興り、たくさんの人たちが働いて、一生懸命焼き物を作っていたということを感じ取っていただければ嬉しいです。

陶石が見つかった「伝陶石採掘地」。採掘は鉱脈に沿って行い、必要に応じてトンネル状に掘り進んだ。
- 中矢:
- 奥にある洞穴のように見えるものが「伝陶石採掘地」と呼ばれているものです。
- 秋元:
- この場所よりも上流の真砂(まなご)や千束(せんぞく)というところでも、古九谷の時代から陶石を採っていたんですか?
- 中矢:
- 恐らくそうですね。千束にも、登り窯の跡らしきものが残っていると言われているんです。古九谷の窯以前に、もしかしたら小さな規模の登り窯が千束のそばで作られた可能性はあります。
- 秋元:
- 試験的にやってみたのかもしれないですね。しかし思ったよりも採掘する穴が小さいですね。去年、花坂陶石の採掘現場へ行った時に「狸掘り」って言葉を教えていただいたのですが、昔は本当に小さい穴で掘り進んでいたようですね。結構、命知らずだなあ。

- 秋元:
- ここには、どれくらいの人が暮らしていたのでしょうか。
- 中矢:
- 大聖寺藩領の記録を記した資料から推測すると、200人ほど暮らしていたようです。ここは山伏等が往来する、いわゆる山の道のハブだったようです。そこを見込んで、九谷の集落に室町時代に成立した浄土真宗の寺院・九谷坊(くたにぼう)や、山の手工業(木地挽物)を背景として集落が繁栄していたと言われています。
- 秋元:
- ここに木地工房があったのですね。
- 中矢:
- そうですね。山中漆器の挽物の工人が住んでいたところになります。ですから古九谷の時代には、木地師も九谷の陶工たちも両方いた可能性は高いですね。

トイレ遺構の様子。現代のトイレットペーパーに相当する「籌木(ちゅうぎ)」も出土している。計14基が見つかった。
- 中矢:
- ここでは水洗トイレの遺構も発掘されています。かなり先進的ですよね。それだけたくさんの人が、ここに住んでいたという証拠になります。

最も残りの良い状態で確認された絵付け窯跡(復元レプリカ。本物はこの下に眠っている)。
- 1
- 2
- 3
- 4








