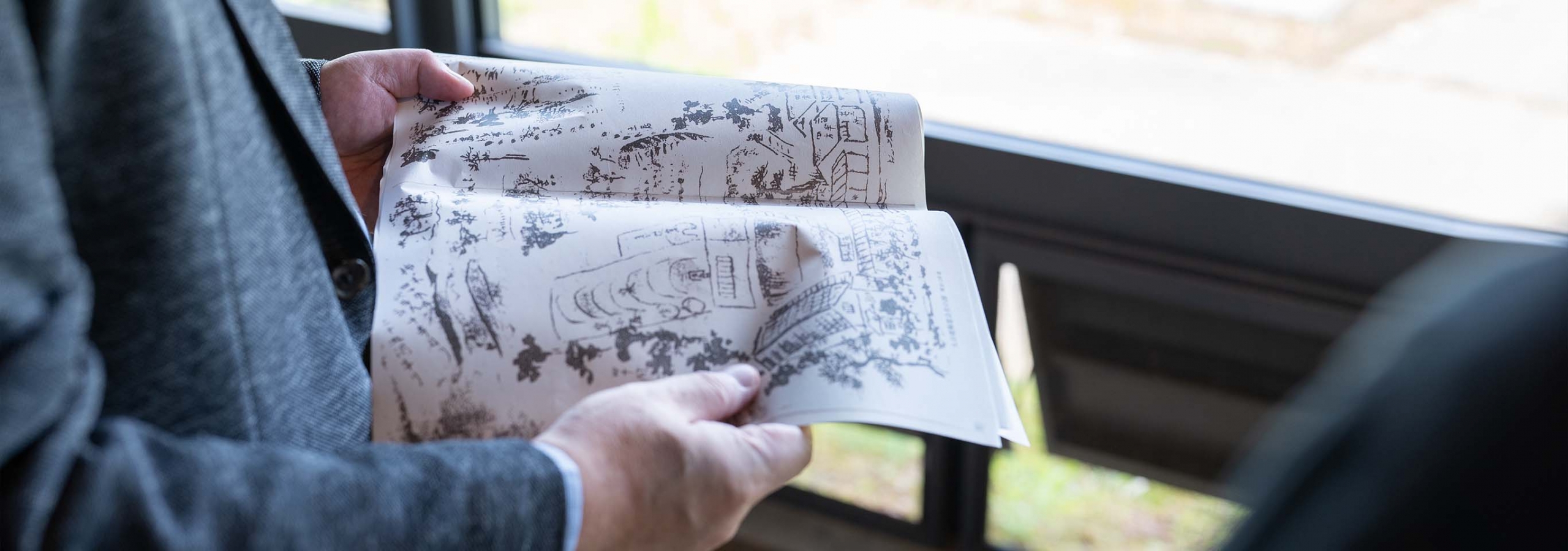

#02
九谷焼の系譜 吉田屋窯、そして古九谷へと遡る
KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで、九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。2021年度は “技法”と“伝承”をキーワードとして、九谷の魅力を、系譜を紐解きながら探っていきます。
第二話では、いよいよ九谷焼の流れを求めて、まずは文政9年(1826)に九谷村(現・加賀市山中温泉九谷町)から山代温泉越中谷に窯が移された吉田屋の窯跡がある「加賀市九谷磁器窯跡展示館」へ。大聖寺の豪商吉田屋伝右衛門が古九谷の美に憧れて開いた窯であり、吉田屋風と呼べる洗練された和絵具による色絵磁器を生産。国指定史跡として保存されています。
その後は場所を移し、更に山奥へ。古九谷の生産地だった加賀市山中温泉九谷町にある「九谷磁器窯跡」を訪れます。今からおよそ360年前、吉田屋窯から数えれば約170年前に作られた二つの登り窯と絵付窯の跡が残り、国指定の史跡となっています。
歴史の奥深さや当時の息遣いを感じる二つのスポットを通じて、古九谷から現代九谷の礎と発展の経緯を探ります。

作品に表れる、当時の自由でのびのびとした空気感。

隣接する母屋は旧窯元だった木造建築を修復。当時は一貫作業を行っており、ここには蹴ろくろ(けろくろ)のろくろ場、はがし場、絵付け場がある。

世界最大の放射光発生装置で成分の組成を検出した結果、九谷古窯製と識別され、正真正銘の「古九谷」であることが認められた作品「九谷古窯製伝世古九谷」(加賀市九谷焼窯跡展示館寄託品)。九谷製の色絵作品が確実に存在することが実証された。

永楽和全作「赤絵金欄手 鳳凰図向附」(加賀市九谷焼窯跡展示館寄託品)。
- 秋元:
- 赤絵も本当に良い作品だ、くぅー!痺れますよね。これくらい描き込んであるといいなあ。途中で気が抜けてないですよね。
- 中矢:
- これは永楽和全ですね。彼は京焼の出身ですが、彼が九谷に金彩(金欄手)を伝えたおかげで「赤絵金襴手」が広まりました。永楽は都合6年間山代にいたのですが、様々な逸話があるんですね。大聖寺のお殿様からもらった小判を潰して金彩にしたとか、お殿様から拝領した羽織を着て、それでろくろを回して作業着にしてしまったとか笑。
- 秋元:
- 面白い人だなあ笑。
- 中矢:
- 永楽は一族郎党(※)を連れてこちらへ来る際に、大聖寺・前田家から十分な藩札をもらって、だいたい3から5年くらいの間、ここに滞在することを契約したみたいなんですね。藩札というのは、その藩でしか通用しないお札のようなものなのですが、それが衣装入れにぎっしりと詰まっていて、それこそ湯水のように使ったというエピソードもあるんです。
(※)血縁のある家族と家来たちのこと。
- 秋元:
- かなり優遇されていたということですね!
- 中矢:
- 大優遇ですよ!幕末動乱の時代に、京都にいるよりも治安がいいし前田公の芸術的センスに応えられるという、永楽としては疎開的な感じはあるものの、芸術を探究した彼にとって最高の職場だったと思いますね。

敷地内には国指定史跡の「九谷磁器窯跡」、加賀市指定文化財の「山代九谷焼磁器焼成窯及び窯道具類」と「旧九谷寿楽窯母屋兼工房」がある。
- 中矢:
- 九谷庄三も18、19歳の頃に、宮本屋窯で赤絵を学んでいるんです。宮本屋窯の前身の吉田屋窯で主工を務めた粟生屋源右衛門から色絵を学んだ庄三は、九谷焼本流の宮本屋窯で赤絵を学ぶことを師の粟生屋から勧められたのではないかと思われます。おそらく「赤絵を勉強するのなら、ちょうど今、飯田屋が頑張っているからあそこで学んでこい」というようなことを言ったんじゃないかなと思います。1年半くらいかな、庄三はここにいて、それから小野窯へ行き、やがて寺井の方で独立するという流れになります。
- 秋元:
- 結構みんな移動しているんですね。
- 中矢:
- 当時の職人たちは、あちこちで修業してます。九谷庄三のように、他の地で色んなものを吸収して九谷に戻ってくるっていうことを色々な職人たちもできるようになったのは、江戸後期からだと思います。江戸初期は、やはり藩をまたいで自由に行き来というのは、関所みたいなのもあるし、とても厳しかったんじゃないですかね。

- 秋元:
- 吉田屋窯にしても若杉窯にしても、それぞれ窯のイメージがあるじゃないですか。それと窯の主要な職人として粟生屋源右衛門なんかがいたわけじゃないですか。窯と名工たちの関係はどうなっていたのでしょうね?
- 中矢:
- 同じ粟生屋源右衛門が作ったものでも、松山窯で作ったものと吉田屋窯で作ったもの、さらに自分で作ったものとでは全く雰囲気が違うんですよね。
- 秋元:
- 色んなタイプの職人さんや作家さん、その中間の立場の人たちも含めて、それぞれに個性があったのでしょうけど、何か決まった型みたいなものがあるわけじゃないですよね。意外と自由だなあと思って。今で言う企業に勤めるみたいな、自分を殺して型にはまるみたいな、そんなでもない。意外と自由な印象ですね。
- 中矢:
- おっしゃる通り、かなり自由だったと思います。吉田屋窯の就業規則が見つかっているんですが、それが非常に面白くてね。吉田屋は造り酒屋をしていたので「夕方4時過ぎになったら、ここで働く人は皆んな自由にお酒を飲んでいいですよ」ということが書いてあったり、それから、おそらく職人に対してですが「もしも病気になったら、みんなで看病して親切にしてあげなさい」って書いてあったり。驚くのが、これ、江戸時代の文化文政の話ってことなんですよね。
- 秋元:
- 面白いなあ笑。

- 中矢:
- こういったことを、吉田屋伝右衛門はきちんと就業規則に書いていた。職人にとって自由な発想のもとでのびのび作陶できる環境が、吉田屋窯にはあったということなんですね。吉田屋窯で生まれた作品を観れば分かると思いますが、あれだけ豊富な意匠デザインで、あれだけ素晴らしいものを、たった7年で作っているのですから、すごいことですよね。それも絵を描いていたのはたった3人という。これは憶測ですが、職人たちは毎日が楽しくて仕方なかったんじゃないかと思うんです。量産はせず一品主義ですから、毎回、新しいキャンパスに新しい絵を描けるんですよね。
- 秋元:
- そうですね。製造をしている場所っていうよりも、ある種のラボ(研究所)のような感じがします。新しい実験をしながら「こういうのもやってみるか!」みたいな。
- 中矢:
- それを許容したのが、教養人・吉田屋伝右衛門だったんですね。やはり彼の存在は非常に大きいと思います。
- 秋元:
- 吉田屋窯の醸し出す空気感というか遊びがある感じっていうのは、職場の雰囲気から出ているんでしょうね。決して工業製品にはない魅力だと思います。
- 中矢:
- このデザインを1000個作るとか、そういう話じゃないんですよね。一つ一つ、違うデザインで作るという。永楽は都合5年ほど吉田屋窯の後継窯「九谷本窯」にいましたが、彼も自由でしたよね。名人気質なので、自分がしている陶器を見て学べと。そういうことを次から次へとやってくれた。ですから九谷が非常に豊かになったのは、前田家と吉田屋伝右衛門と永楽和全のお陰だと私は思います。
九谷焼のルーツが見つかった場所
- 1
- 2
- 3
- 4








