作家×キュレーター対談「小松の九谷焼と自作について」 2021年9月19日、KUTANism関連イベント「作家 × キュレーター対談」が開催されました。午後の部は、小松市出身・在住の陶芸家・𠮷田幸央さんと展覧会「高雅絢爛展-九谷焼の今-」のキュレーターを務めた国立工芸館主任研究員・岩井美恵子さんが「小松の九谷焼と自作について」をテーマに対談。当日の様子をダイジェストでお届けします。

- 岩井:
- 県外から見た九谷焼は「石川の加賀地方で制作されている、華やかな絵付けが特徴の焼き物」というイメージが強いと思うのですが、今年4月に石川に赴任して改めて九谷焼というものを学んでいくなかで、加賀地方のなかでも地域によって少しずつ特徴が異なる印象を受けました。この対談では小松エリアの九谷焼について、錦山窯の𠮷田幸央さんに話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
- 𠮷田:
- これまであまり公開してこなかった僕の制作環境や制作プロセス、また僕が制作において何を大切にしてきたかということをお話しながら、小松エリアの九谷焼の特徴が垣間見えるような内容になればと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。
錦山窯の制作環境と作業工程について
- 𠮷田:
- 錦山窯では床にあぐらを組んで座るスタイルをやめて白いテーブルを導入し、非常に明るい工房に模様替えしました。自分のテーブルを自由に使えるので、スタッフのみなさんからも好評です。

錦山窯の工房。
- 𠮷田:
- 次に金箔です。うちの窯にとって最も重要なものは金(きん)です。金を使わない作品はないくらい錦山窯では金を使います。制作工程のうち金粉作りはとても重要なパートです。一日がかりで金を擦りつぶして水簸(すいひ)をして細かな不純物を取り除きます。なぜここまで手間のかかる作業を行うかというと、コスト的には自家製の方が高くなるのではと思うのですが、時間をかけて手作業することで非常に粒度が細かい金が取れる、すなわち金を差別化することができるんです。


- 𠮷田:
- これは色付け前の素地です。僕はフラットな面にペイントするということに対して違和感を抱いてきました。30代半ば頃、「質感」に対してのこだわりをどのように表現できるかと考えたときに、上絵付けをする前の段階、素地作りの重要性に行き着きました。自作を語る上で僕にとって素地、言うなればキャンバスを作る作業は非常に大切です。一般的には素地を引いてその上に釉薬をかけて焼成するのですが、僕の場合は素地に泥漿(でいしょう)を薄く叩きつけて、その上から手の感覚を使ってなじませることにより表情を付けています。これを素焼きした後、さらに釉薬で凹凸を付けながらキャンバスを作っていきます。大変体力を使いますが、自分の色を出すためには欠かせない作業です。

- 𠮷田:
- 上絵付けはこの6色をベースにしながら、なるべく多くの洋絵の具を重ねていくのが僕のやり方です。さきほどのキャンパスに少しずつ色を重ねては焼き、重ねては焼きという作業を何度も行います。色を混ぜるのではなく、薄い色の重なりで深みを演出するのはこだわりです。そのために、先ほどお話した素地の質感が必要なんですね。塗り絵の作業は最低でも4回、多い時で5、6回繰り返します。僕は色を塗る作業が大好きで、この至福の時間があるから頑張れます。

- 𠮷田:
- 色絵が終わったら、その上から金彩を施していきます。僕の父であり人間国宝の𠮷田美統は釉裏金彩(ゆうりきんさい)の第一人者で、僕はその技術を用いています。医療用のハサミやピンセット、ハケが代表的な道具です。また、レーザーカッターでデータ入力して金箔をカットすることもあります。その上からさらに金彩を施していきます。
淡い色を何層にも重ねることにより表現される奥深さ
- 𠮷田:
- フラットな素地にテクスチャーをつけて、何回も水彩画のように色を重ねて色彩の奥深さを表現するのが私のテーマです。初めの頃は現在よりも色が強く、白い部分をあえて残して色とのコントラストを魅せるようなものが多かったのですが、だんだんと色が薄くなり、ぼんやりとした色彩のなかでテクスチャーが浮かび上がってくるような表現に変わってきました。僕は色をたくさん使わないと気が済まない性格で、内側と外側に違う色を使うことが多くあります。こういうところが九谷っ子なのかなとも思いますね。また、最近ではどんどん金箔の使用量が増えてきています。金を貼るのがとても楽しくなってきて、抑えが効かなくなってきているというか、自分のやりたい表現に素直でありたいと思っています。

- 𠮷田:
- 作品は飾るのではなく、ぜひ使ってほしいと思っています。料理を載せたり花を生けたり、ワインクーラーとして使ったりと使い道は様々あります。金箔は何度も使用することにより剥がれ落ちていきますが、それ自体を経年変化として、また一つの味わいとして楽しんでいただければという思いです。

- 𠮷田:
- 2019年にギャラリー「嘸旦」が誕生しました。広さとしては6人ほどしか入れないのですが、ここでシークレット的にイベントを開催して、お茶会をしたりワークショップを行ったりしています。ギャラリーを作った理由は、とにかく器を使ってほしいという思いがあったからです。九谷焼は絵付けが豪華ですので実際に使用することに対して抵抗感がある人もいらっしゃるとは思うのですが、様々な使い方をお伝えしたり、金が剥げていくことも味わいが変わって素敵だということを知っていただいたり、そういった文化を伝えていきたくて、この場所を作りました。「嘸旦」には「何もないところから始まる」という意味を込めています。この場所から、新しい九谷焼の意義を伝えていきたい。実際に訪れて、器を見て使ってみていただきたいと思っています。
自分らしさの「解放」が色彩豊かな表現に

- 岩井:
- 「フラットなキャンパスが好きではない」というお話がありましたが、それはいつ頃から感じ始めたのでしょうか?また、作陶を始めた当初はシンプルな作品を作っていらしたようですが、それが現在のような色彩豊かな表現へと変化したのには、何かきっかけがあったのですか?
- 𠮷田:
- 家業に入り絵付けの手伝いをしながら作家活動をしていたとき、あるとき身の回りにある様々な情報に押し潰されそうになって、つらくなったことがありました。次の展開を考えたときに、自分の表現というものがどこにあるのか分からないような感覚に襲われたんですね。そのときに思い切って器を作り始めたのですが、それが楽しかったんですね。1994年に高岡クラフト展で金賞を取って、改めて作る面白さを感じたというか、自分に合っている感じがしました。ですので、自分を解放するために少しずつやりたいことが変わってきたような気がします。
- 岩井:
- その「解放」が現在の色彩豊かな表現につながっていくのですが、色彩の豊かさは外から見た九谷焼の特徴でもありますね。𠮷田さんが考える九谷焼、九谷焼という言葉が指す表現はどのようなものだと思いますか?
- 𠮷田:
- 九谷焼というと、地元では徳田八十吉先生や浅蔵五十吉先生など僕の父と同世代の先生方の作品が真っ先に頭に浮かびます。先生方は色絵や金彩、釉裏金彩のような新しい技術も含めて九谷らしい伝統技法を継承しながら表現を展開していますよね。
九谷焼の産地としての小松の特徴とは
- 岩井:
- 九谷焼の産地としての小松の特徴をどのように考えていらっしゃいますか?
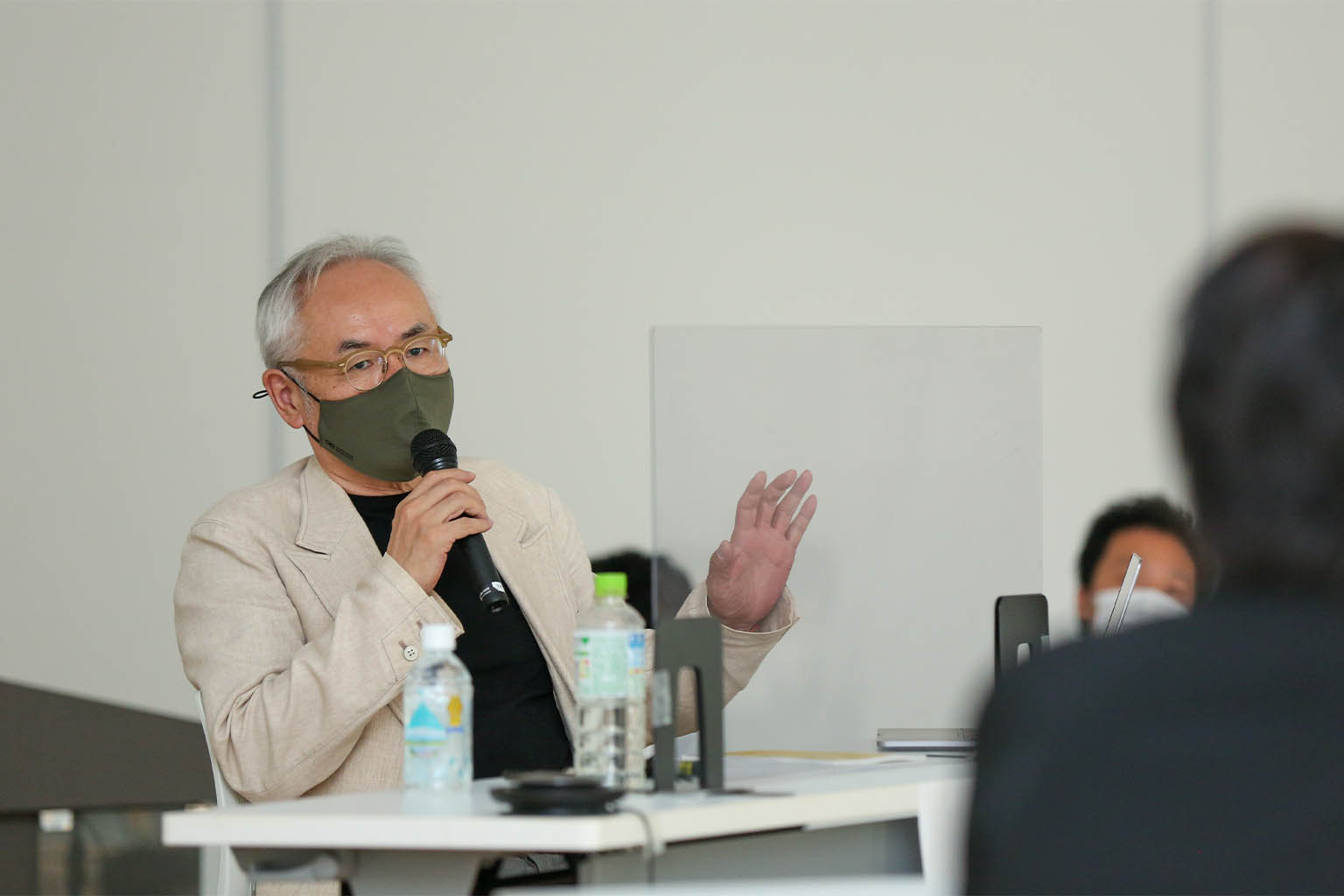
- 𠮷田:
- 言葉にするのが難しい質問ですね笑。行政区で言うと、加賀市には石川県立九谷焼美術館、能美市には九谷陶芸村や能美市九谷焼美術館などがありますが、小松市は2019年に「九谷セラミック・ラボラトリー」がオープンしました。また花坂陶石という九谷焼の原料が採れて製土所があること、「九谷窯元組合」という素地を作る専門の職人たちが多いことが小松の特徴なのではと思います。九谷焼の製造に関わる人が多い一方で、流通や小売に携わる人がほとんどいない、作り手オンリーの土地柄というところが面白いと思います。
- 岩井:
- 流通や小売に携わる人が少なく作り手がほとんどという特徴が、作家活動や作風に与える影響はありますか。
- 𠮷田:
- 面白いのが、九谷焼で人間国宝に認定されている私の父と三代・徳田八十吉さんは二人とも小松出身ということなんですよね。感覚的ですが、小松市は伝統的な技術が濃厚に残っているエリアのような気がしています。青粒や毛筆細字など非常にマニアックな技法が今なお残っていて、それを継承している若い作家がいるんですね。一方で能美市は流通が盛んですので、そういった方々が日本全国、さらには世界に九谷焼を広げていった歴史がありますし、今もそうであると思います。金沢は「金沢美術工芸大学」や「金沢卯辰山工芸工房」といった教育機関があり、大きな美術館やギャラリーも多くありますので、情報発信をしたり技術を習得したりする場というイメージがあります。土地土地によって特徴が異なりますね。
- 岩井:
- 金沢や能美には教育機関がありますが、小松市には九谷焼を学ぶ場がありませんね。
- 𠮷田:
- まさしくそこが課題だと思っています。九谷焼を学んだり、また教育機関がなくとも作陶に適した環境や制度を整えることで、県外から小松市を訪れ、九谷焼の作家や職人として活動をする若い人が増えるのではと考えています。
多様な表現や技法が集まった「九谷焼の今」

- 岩井:
- 例えば県外の方から「九谷焼とは何ですか?」と聞かれたときに、𠮷田さんはどのように答えますか?
- 𠮷田:
- 実は一番されて困るのが、その質問で笑。単純に「多様性です」と言ってしまう場合もあるのですが、それもちょっと違うような気がしています。この土地には様々なコミュニティや色々な個性を持った人たちがいて、そういったコミュニティや人々の交流のなかで生まれてくる作品というのは、ものすごく多様性があるのですが、どこか九谷焼っぽさというものが含まれている感じがするんですよね。それが土地柄、土地が醸し出す雰囲気なのかなと思います。
- 岩井:
- 九谷焼には様々な表現を受け入れているからこその、多様性がありますよね。今回の展示からも分かるように、技術も表現方法も相当幅広い。若手作家の作品を見ながら「これは九谷らしくない」などと言って排除しない、むしろ積極的に評価していく上の世代の存在があるからこそ、これほどまでバリエーション豊かな表現があるのではと思いました。
- 𠮷田:
- 僕自身、普段はあまり九谷というものを意識していないんですね。この土地で、僕が使える素材や技術を使って何かを表現しようとして生まれたものに九谷焼のエッセンスが表れているような感じでしょうか。私が前半で作業工程や使用道具をご紹介した理由は、それらから地域性や九谷焼らしさというものが伝わる気がしたからなんです。

- 岩井:
- 焼き物は日本の伝統的な文化であり産業なので、九谷焼に限らず美濃焼や萩焼といった言葉が古くからずっと残っていますね。一方で時代と共に表現や技術というのは変化しているので、現代における「〇〇焼」という言葉の使い方がすごく難しくなっているように感じます。作家の方々は九谷焼という言葉をどのように捉えて、また九谷焼の産地でどのような思いを持って制作活動をしているのでしょうか。
- 𠮷田:
- 「九谷焼」は、この地域の焼き物の産業をまとめて紹介する一種のキーワードと言いますか、象徴的な言葉になっていますね。僕は絵付け作家であり金襴手を表現の一つとして制作を行っていますので、古くからある九谷焼の技法を取り入れている立場としては「九谷焼の作家の一人」と言われることにそれほど違和感はありません。ただ、自分で「九谷焼の作家」を名乗ることには違和感がありますし、先ほども申し上げましたが「九谷焼とは?」と聞かれたときに困ってしまいます。古九谷や再興九谷の作品をイメージして「九谷焼」を考えると、非常に現在の状況が解釈しにくいんだろうと思いますね。
- 岩井:
- 展覧会では今回「技」をテーマにしましたが、作家によって表現方法が様々ありますし、古九谷や再興九谷のイメージとは異なるものがほとんどです。「九谷焼の今」というサブタイトルを付けたのは、「九谷焼の今」はこれだけの表現や技術のバリエーションがあるということを表現したいと思ったからです。リアルで観ていただくことにより、それが伝われば良いと思います。




