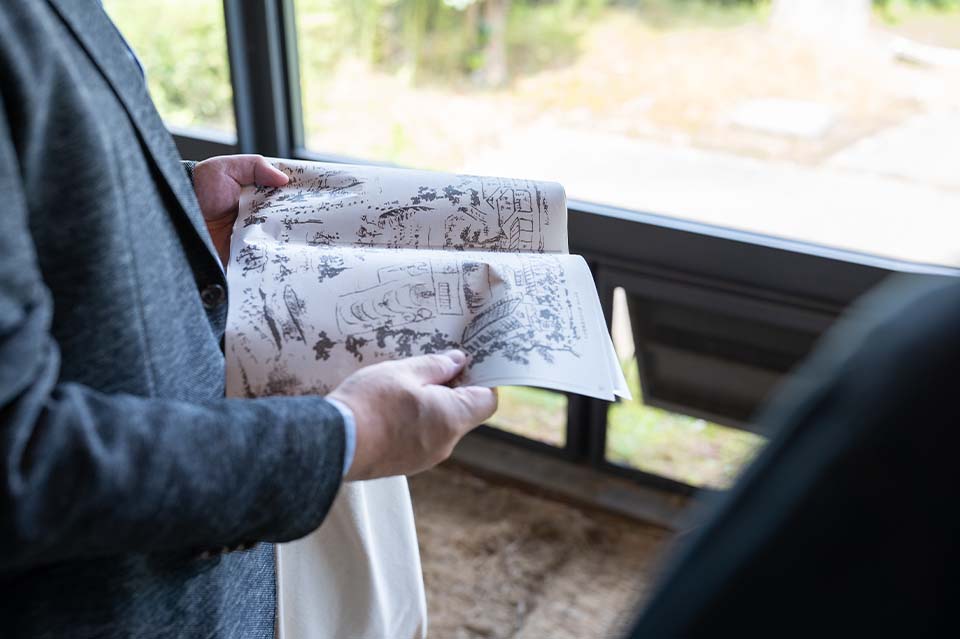#04
代々伝わる“色”を守りながら、作家としての個性を表現する
KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで、九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。2021年度は“技法”と“伝承”をキーワードとして、九谷の魅力を、系譜を紐解きながら探っていきます。
第4話から第6話は「技法の継承と個性」をテーマに、九谷焼を代表する技法と技の引き継がれ方に迫ります。今回伺ったのは三代・浅蔵五十吉さんが窯主を務める「深香陶窯(しんこうとうよう)」です。
九谷焼の伝統に現代感覚を取り込み、独自の世界を切り拓いた九谷焼を代表する名工、二代・浅蔵五十吉。その後を継いだ三代・浅蔵五十吉さんは、先代が生んだ「五十吉カラー」と呼ばれる色彩表現をさらに発展させ、造形的な成形と組み合わせて表現の幅を広げた作品を作り出しています。戦後の九谷焼界をけん引した二代の後を継ぐこと、また次世代に技をつないでいくことについて話をお聞きしました。

作家になるためには、まず自分の手で形を作ること。
- 浅蔵:
- やはり原点は、自分の手で形を作ることだと考えています。ろくろを最初に学んで、茶碗にしても花生けにしても、自分で作る。「作家になるために、まず職人になれ」。これは第一条件だと思うんです。何も形を作れないのに作家を名乗る人は、どこにもおりませんから。九谷焼は粘土から無限の形を作るので、どうしても技術がないとできませんからね。父は「真理は技術」とよく言っていました。道具を使って形を作るにしても、その道具も自分で作らなければいけないよと。
- 秋元:
- 作品を作る上で一番重点を置いているのはどんなところですか?
- 浅蔵:
- 私の場合は、形はもちろんですが、最終的には図案と色が大切だと思いますね。形はある程度オーソドックスなものが多いです。
- 秋元:
- 図案や色を一番生かせるのは大皿のような形でしょうか。

中央が三代・浅蔵五十吉さんの作品。
- 浅蔵:
- そうですね。それと、刻彫(こくちょう)と言って、形を作った上に粘土で肉付けしたり竹ベラなどを使って線を引いたりして、形自体に模様を付ける場合もあります。九谷の場合は綺麗で歪みのない皿に絵を付けることが多いですが、私の父はどちらかというと、刻彫した上に絵付けをすることが多かったですね。
- 秋元:
- 絵を描くための土台として形もしっかり作らないといけない、という感じでしょうか。
- 浅蔵:
- そうですね。場合によっては先に図案を書いてしまって、その図案に合った形を作ることもあります。
- 秋元:
- 上絵付けについてお聞きしたいと思います。色々な描き方があるかと思いますが、いくつか窓絵(※)を組み合わせて全体を構成する人もいれば、一枚の絵として考えていく場合もあるでしょうし、皿の場合は上下左右がありますよね。焼き物における絵は、どのように考えれば良いのでしょうか。
(※)窓絵/枠を設けてそのなかに絵を描くこと。
- 浅蔵:
- はじめに紙に下書きをしますが、立体ですので上絵付けの際に筆で直すことはありますね。やはり描きやすいのはお皿です。
- 秋元:
- 平らな面はできるだけ多くあった方がいいということでしょうか。やはり絵として描いているということですね。私は絵画出身なので、絵というと前後左右や奥行きを想像するのですが、立体的な焼き物に絵を描く場合は通常の絵画とは違ったこだわりがあるのではと思います。

三代・浅蔵五十吉さんの作品には椿をモチーフとしたものが多い。
- 浅蔵:
- そうですね。例えば立体的な焼き物に鳥を描く場合、まず初めに鳥を描く場所を決めて、続けて必要があれば鳥と関連したものを周りに描いていきます。花生の場合でしたら正面に持ってきたい絵柄を決めて、そこから後ろに向かって展開図のように描いていくんです。
父から引き継いだ釉薬の調合表、終わりのない“色”の追求
- 秋元:
- 浅蔵さんの作品は色が一つの特徴ですよね。
- 浅蔵:
- 私は五彩の色をミックスして、少し変わった色を作りました。「浅蔵五十吉の色」とよく言われる結晶を含んだような黄色っぽい色は、父の代からずっとある色なんです。ただ私の代と父の代では、やはり結晶の出方や癖が若干違いますね。同じ調合表を使っていても、調合の仕方によって絶対に同じ色というのは出ません。父から色をもらったときも、しばらくは失敗ばかりしていました。
- 一華:
- しまいには水が悪いんじゃないかって笑。
- 浅蔵:
- ただ、失敗を繰り返しているうちに面白い色がポンと出てくるんですね。それを私の色として使うと。私はかつて名古屋にあった「国立名古屋工業技術試験場陶磁課(現・産業技術総合研究所中部センター)」で色の勉強をしたのですが、そこで「九谷焼は色が大事なんでしょう。色はね、黄色を作るにしても紫色を作るにしても、“これで完成”というものは無いんですよ」と言われたことが印象に残っています。なぜかと問うと「一番大切なのは原料です。原料は必ず変わりますよ」と仰ったんですね。「原料の調合によって、ものすごく幅が広がります。だから色の勉強をすると非常に面白い。描くことも大事ですが、合間を見ながら色んな調合を試してみなさい。冒険のなかに新しいものが出てきますよ」と。それが今でも心の中に残っています。

- 秋元:
- 浅蔵さんが焼き物の世界に入ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
- 浅蔵:
- 家業でしたので、そこは迷わなかったですね。
- 秋元:
- お父さんに弟子入りする形だったのですか?
- 浅蔵:
- 私は石川県立工業高校を卒業した後、元々は美大に行く予定にしていたんです。そうしたら、父と付き合いがあった北出塔次郎先生に「大学に入るよりも実際の現場で学んできてはどうか」と言われて、それで国立名古屋工業技術試験場に入所しました。そこでは粘土の作り方から釉薬の作り方、ろくろの引き方、窯の炊き方まで全てを教わりました。彫刻の先生と出会って、彫刻についても習いましたね。二年間の研修から帰ってきて北出塔次郎先生に弟子入りし、二年間学びました。

設備が整った工房。以前は多くの職人が働いていた。型倉庫には初代が使用していた型も残る。上絵付けはそれぞれ別の場所で作業を行う。
- 秋元:
- 実家に戻ってきてから、お父さんとの関係はどのような感じだったのでしょうか。
- 浅蔵:
- 父は、人にものを教えるということはあまりなかったです。ただ「作家になりなさい」とは言われました。「自分の作品を作る以上は、他人に作品を見てもらって、評価を得て初めて作家になるのだ」と。それから日展への出品を始めました。人から作品を見てもらって意見を聞くのは、やはり大切なことだと思いますね。

三代・浅蔵五十吉さんの日展初入選作品「岩層」。
- 秋元:
- 今はどのくらいのペースで展覧会に出品しているのですか?
- 浅蔵:
- 最近は日本現代工芸美術展と日展だけですね。時々グループ展にも出品します。以前は東京でもよく個展をさせていただきました。
- 秋元:
- 展覧会の在り方というのは、昔と比べて変わったように感じていらっしゃいますか?
- 浅蔵:
- 時代と共に変わってきたと思います。過去に日展で賞を取ったとか、作家の名前で売れる時代ではもう無くなってきていますね。
- 浅蔵:
- しかし、焼き物の世界ほど奥深いものはないですね。九谷だけでも相当幅広いですから。だからこそ、何をどうしたら良いかと迷う若手もいるんじゃないかと思います。一生のうちに、自分の作風として何を残していくか。そんななかで、人を育てるという宿命的なものが、何か私たちに課せられているんじゃないかと思います。

「深香陶窯」のギャラリーには様々な作品が展示されている。
- 秋元:
- 一華さんと宏昭さんは現在、どのような活動をしているのですか?
- 宏昭:
- 首都圏のデパートで発表するなど、個展やグループ展を中心に活動しています。陶芸を始めたばかりの頃には公募団体展にも出品していましたが、最近は出していないですね。
- 秋元:
- 時代も変わってきていますからね。それぞれご自身の仕事については、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
- 一華:
- 私としては全然難しく考えていなくて、とにかく目の前にある仕事に集中するようにしています。予定しているグループ展や個展に合わせて少しずつ制作を進めたり細かい作品を作ったりして日々が回っている感じで、あまり難しく考えるとかえって制作ができない気がするので、気負いすぎず細々と続けていきたいと思っています。
- 秋元:
- 近年では作家さんが外部とコラボレーションすることも増えてきていますが、そういった取り組みは何かされていますか?
- 宏昭:
- 僕たちが参加している、小松市や九谷焼作家などでつくる「こまつKUTANI未来のカタチ」というプロジェクトがあるのですが、その取り組みの一貫として、地元企業の小松マテーレ、多摩美術大学の学生とコラボレーションした作品を作り、2021年3月に東京・ミッドダウンのギャラリーで展示をしました。一華さんが図柄を考案・上絵付けをし、私が傘立ての制作を担当しています。

コラボ作品「九谷傘 氷雨」。手描きの柔らかさや上絵の具の表情、小紋の細かさが表れるよう試行錯誤して手掛けた。
- 秋元:
- 面白いですね。去年からずっと取材をしてきて、九谷には色々な可能性があると思うのですが、やはり新しく必要とされる場所をどう作っていくのかという課題があるように感じています。それは作り手だけが提案するのではなく、誰かと手を組んで新しいものを作るという方法もありますし、様々な展開をしていく時期にきているような気がします。一華さんがこの道に進んだのはどういった経緯だったのでしょうか。
- 一華:
- 若い頃は、いわゆる反抗心なのかも知れないけど、「うちを継がなきゃ」ってことは考えていなかったんです笑。高校生になって進学先をどうしようかと考えたときに、父は何も言わなかったのですが母が美大を勧めてきて。祖父たちが夜遅くまで仕事をしている姿も見てきたので、少しでも家業を手伝えればと思い金沢美大に進みました。
- 秋元:
- 作家活動をするなかでのこだわりは何ですか?
- 一華:
- 九谷らしい絵付けも大事だけど、そのなかでも自分なりの文様だったり模様だったりを作っていきたいと思っています。

一華さんの作品は、伝統的な小紋を様々な形にアレンジして絵付けをしており、細かい文様と大胆な模様の組み合わせが特徴。
- 秋元:
- 釉薬の調合というのはご自身で行っているのですか?代々続く「浅蔵五十吉」を継ぐことに対してはどのように考えているのでしょうか。
- 一華:
- まだ絵の具の調合は父から教わっていません。先ほど暗号で書かれた調合表と言っていましたが、見たこともないしどんなものなんだろう笑。受け継ぐのはギリギリになると思います。父は私の仕事に口を出してこないし、私も教えてほしいとか言わないし、親子ってそんなものなんじゃないでしょうか。「浅蔵五十吉」をどうしても自分が継がなきゃいけないとは考えていないです。ただ五十吉を名乗る名乗らないは別として、とりあえず九谷焼を作るということは、私たちの代は一生懸命続けていきたいと思っています。
この回のまとめ
- 1
- 2
- 3